「イエネコ(アメリカンショートヘア種)の全ゲノム解読に成功」
2020年5月22日、アニコム先進医療研究所株式会社が発表したニュースです。
ゲノム(全遺伝子情報)解読が成功したというのは、
という意味です。
身体の設計図によって、病気の原因を探って診断や治療に役立てたり、遺伝的な病気のなりやすさを知って事前に予防できるようになります。
猫ちゃんの遺伝的な病気の治療にもようやく希望の光が灯ったようです。
ちなみに人の設計図が出来上がったのが2003年。
それから18年たった今、ようやくお酒に強いかどうかといった体質や、がんや糖尿病、脳卒中、高血などの病気になりやすいかなどの情報が提供されるようになりました。
最近ではアンジェリーナ・ジョリーのがん予防のための乳房と卵巣・卵管の切除手術が注目されましたね。
遺伝子情報の解析結果をもって、がんを治療するにはまだまだ時間がかかりそうです。
猫に対しての治療は、果たしていつになるのか?
アメショの心筋症、スコティッシュの骨の病気が、治る日が来るのか?
というわけで、今回のこの研究はどんなことを行って、この先どんなことができるようになるのか?
これらについて考察してみたいと思います。
アニコムによるアメショのゲノム解読の概要
アメリカンショートヘアの全ゲノム解析を19本の染色体レベルでほぼ全長、高精度で行った。
人間の染色体は23本×2=46本。これに対して、猫は少なくて19本×2=38本。
※”×2″というのは父親、母親それぞれから受け継ぐので”2倍”です。
★今回の研究は「アメショでの解析」というのがポイント!!
- 実は2007年にアビシニアンのゲノム解析はできていたものの、他の品種に参考になる遺伝子が少ないことや、まだ構造に関してわかっていない部分が多かった。
- アメショは人気があって数も多く、マンチカンやスコティッシュなどの交配が認められていたりして、遺伝的にたくさんのねこ種の解析に役立つ。
- アメショはアメリカ大陸に初めて上陸したネコが祖先。そのためイエネコの様々な品種がどこからやってきたのか?、どのネコから派生したのか?を知る手掛かりになる可能性がある。
アメリカンショートヘア種とアビシニアン種との配列を比較したところ、両者は染色体の一部で異なるゲノム構造をもっていることがわかった。
- アメショとアビシニアンの違いを比較することで、アメショでよくみられる肥大型心筋症などの遺伝病の原因と治療法に役立つ。
- アビシニアンが元気で活発な理由が分かったりする。
ゲノム解読によって何が変わる?「ゲノム獣医療」を具体的に解説
ヒトのゲノム解読にも時間がかかっているくらい難しいことなんですが、今回のアメリカンショートヘアのゲノム解読に成功したことで、例えば「アメショに特徴的な病気」や「体質に関わる遺伝子の研究」だけでなく、「イエネコ全体のゲノム獣医療(遺伝子情報から効率よく効果的に施す動物のための医療)」が進みます。
今までの治療では…
どの猫にも同じ治療を行っていて、
効果があったり…
効果がなかったり…
ゲノム獣医療が行われると…
遺伝子情報に基づいて、猫それぞれの体質に合わせた治療を行うことができるようになります。
効率よく効果的に、病気を診断したり治したりできるようになるんですね。
さらに他の種のゲノム解読によって…
例えばスコティッシュフォールドやマンチカン、ペルシャなどのゲノム解読ができれば、この猫種によくみられる関節の病気「骨軟骨異形成症」や腎臓の異常「多発性嚢胞症」が治療できるようになったり、
ノルウェージャン、メインクーンの解読ができると、貧血が起こる病気「ピルビン酸キナーゼ欠損症」や失明することもある「進行性網膜萎縮症」などの治療に役立つ可能性があります。
ゲノム解読の意味
上の説明の通り、ゲノム解読が進み、ゲノムを編集することができるようになると、「病気になりにくい猫」や「人を猫アレルギーにさせない猫」を生み出せるようになるんですね。
病気にならないことで、猫は辛くないし、飼い主も医療費の負担が減る。
この一見、メリットだらけにも思える、病気にならない猫は、言い換えると「飼いやすい猫」とも言えます。
「飼いやすい猫」が増えることで、需要が増え、市場が大きくなり、今よりも悪徳業者が増える可能性だってあるんです。
素晴らしい技術によって病気の猫が救われる一方で、使い方を一歩間違えると、
人間の金儲けに利用されてしまう。
他にも、農業や畜産業でも問題となる、遺伝子組み換えによる品種改良やクローン技術。
それはペットに対しても同じことで、倫理観が問われることにもなるんです。
まとめ
人間では、ひとそれぞれに合わせた医療を「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」として、文部科学省が主導で進めています。
その他、がんの治療についても、がんを抑える遺伝子やがんをやっつける遺伝子を組み込んだり、抗がん剤の副作用を抑える遺伝子を組み込んで、副作用をなくしたりする治療の研究も行われ、実際一部が保険診療として「がんゲノム医療」が行われ始めています。
実際に猫に「ゲノム獣医療」が行われるのは、もうちょっと先になりそうですが、今回の成果を前向きにとらえると、
実現すれば、猫が病気にならず元気でいられる年数「健康寿命」を延ばしたり、病気を予防することができるようになるんですね。
令和2年時点の猫の平均寿命は、15.45歳。
たくさんの猫が、元気に20歳を超えても生き続けられる日が、近いのかもしれません。
10年ほど前にがんで亡くなった猫は、最後、足が腫れて相当痛い思いをしたんだと思います。
もし当時ゲノム獣医療が治療できていれば、痛い思いもせず、今年30歳で元気だったかな?と思ったり・・・
今、まさに病気で困っている猫もたくさんいると思います。
そんな子たちのためには、一日でも早く実現してほしいなと思います。
参考:東京大学|ネコゲノム解析プラットフォーム、埼玉県獣医師会|猫の遺伝性疾患について、アニコム先進医療研究所株式会社|ゲノム獣医療への応用を目指して
参考記事:【猫はいつ誕生したのか?猫の祖先は?】~ネコとヒトが出会った日
参考記事:【世界で一番古い猫】マヌルネコってどんな猫?
参考記事:【猫とマタタビの話】『ネコにマタタビ、おじょろうに小判』
参考記事:【猫にミネラルウォーターを与えてもいい?悪い?】水道水との違い
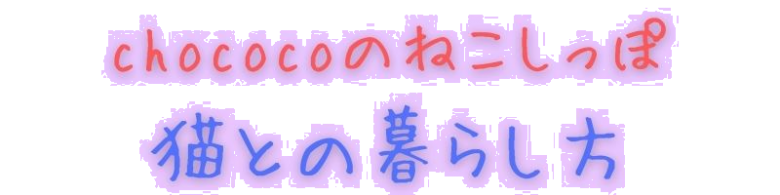







コメント