猫を迎え入れる方法のひとつとして、保健所で保護しているねこを譲渡してもらう、いわゆる「里親募集への応募」があります。
- 里親になるための流れ
- 保護された猫はどこでどうやって引き取る?
- 保健所以外に里親募集している?
- 里親になるにはお金がかかる?
今回は里親を募集している各都道府県、市の自治体、保護団体、ショップなどから
猫を引き取るための方法や引き取りまでの流れ、条件について紹介します。
これから猫を迎え入れたいと考えている方の参考になればと思います。
関連記事:【賃貸・初心者・一人暮らし必見!】猫を飼うための極意!!
里親申込みから迎え入れまでの流れ
各都道府県には必ず「動物管理センター」や「保護センター」があり、里親を募集しています。
その他にもNPO法人などの保護シェルター(施設)やペットショップや猫カフェでも
募集していたり、譲渡会なども開かれます。
※ただし2020年8月現在は、募集を見送っている施設があります。
里親の申し込みから迎え入れまでの流れは、募集先にもよりますが、ざっくりと以下の通りです。
- 公式サイトを確認するなどして応募先へアクセスする。募集先によっては、会員登録が必要なところも。
- 里子として迎え入れたい猫ちゃんを探し、応募登録を行う。
- 募集者へ連絡し、面談日程を決める。
- 面談、猫ちゃんとも顔合わせ。引取り条件の確認をします。
- 施設によってはトライアル(お試し)期間を設定しているところも。
- 引き取り。
費用については、0~3万円程度と、購入ほどではないにしろ、費用がかかるところがほとんどです。
そして購入する場合と異なるのは、飼うための条件が厳しいことです。
理由は、再び飼育放棄で施設へ戻ることを防ぐためです。
引き取りは必ず直接手渡しになりますので、お近くの施設の情報を確認ください。

里親募集先と手続きの流れや条件
それでは次に、様々な募集先の譲渡までの流れ、条件をまとめてみました。
主な都道府県の動物管理センター
東京都 動物愛護相談センター
大阪府 動物愛護管理センター
愛知県 動物愛護センター
主な譲渡の流れ
- ウェブサイトで飼い主になるための流れ、条件確認
- 各センターへ連絡、譲渡前調査、面談などの日程調整
- 飼う前の心構えと準備の説明(譲渡事前講習会)
- 犬・猫とのお見合い/適正な飼い方の説明(譲渡講習会)
- 書面等による手続き、引き取り
※譲渡事前講習会を実施しない自治体もあります。譲渡事前講習会の日程は必ずウェブサイトをご確認ください。
飼い主になるための条件
- 飼い主に対し、各都道府県ごとの年齢制限あり
- 先住動物がいる場合、譲渡不可の場合あり
- 家族の動物に対するアレルギー有無の確認
- 室内飼いが必須の自治体あり
- 飼うことを家族全員が賛成していること
- 最期まで責任を持って飼い続けることができること
- 経済的、時間的に余裕があること
- 動物に不妊去勢手術による繁殖制限措置を確実に実施できること
- 集合住宅・賃貸住宅の場合は、飼育許可を確認できる書類
必要なもの
- 住所と本人が確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
- センター主催の譲渡事前講習会のテキスト(受講者番号が記載されているもの)
- 筆記用具・印鑑
- ケージ、キャリーバッグ等
- その他センターの指定する書類(同意書、集合住宅管理規約等)
- 譲渡に係る諸費用(~1万円程度)
その他県、市の動物管理センター
※過去に、動物の飼養等に関する指導等を受けたなど、飼育困難と判断できる場合に、引き取り出来ない場合があります。
NPO法人、保護団体など
千葉県柏市、岐阜市、名古屋市
譲渡の流れ
- ウェブサイトにて、「里親募集の説明」を確認する
- 面会空きスケジュールを確認して申し込みフォームから申請
- メールにて「面会受諾のお知らせ」を受け取る
- 面会
- 成猫に限り希望者には、「トライアル飼育」を実施(1か月程度)
- 誓約書記入・捺印の上、引き取り
飼い主になるための条件
- 完全に室内で十分なスペースで生活していただけること
- 飼育について家族全員の同意が得られていること
- ご家族の一員として迎え入れていただくこと
- 猫を飼育できる住居(ペット可が明示されている物件)にお住まいであること
- アレルギーの有無の確認や、必要に応じて医師と相談をしていただいていること
- 終生愛情と責任を持って飼育し、ライフボートの許可なしに他人への再譲渡をしないこと
- 伴侶動物としてのみ飼育し、再譲渡・販売・貸出し・展示・動物実験などに利用しないこと
- 20歳以上で動物を終生飼育する経済力があること
- その他、適切な飼育と健康管理が可能なこと
- 飼育者が60歳を超えている場合、制限あり
- 小さい子供がいる場合、保護者が猫の扱いについて監督できる家族
譲渡が難しいケース
- 先住動物との相性が心配・先住動物の数が多い
- 引越しを控えている
- 未成年者のみでの面会やサプライズプレゼントなど
- 日本語が十分に通じない場合
※上記はあくまで一例で、団体の判断で譲渡をお断りする場合があり。
必要なもの
- ケージ・キャリー等
- 顔写真と住所と生年月日の確認のできる身分証
- 印鑑
- 賃貸住宅や集合住宅の場合は、ペットの飼育条件が明記された契約書や規約のコピー
- 譲渡に係る諸費用(~3万円程度)
インターネットの募集サイト
譲渡の流れ
- ウェブサイト上で会員登録
- 希望の猫が決まったら、ウェブ上で依頼者(掲載者)とやり取り
- 依頼者(掲載者)と事前に面会の上、誓約書記入し譲渡決定
- 手渡しにて引き取り
飼い主になるための条件
- 転売目的での譲受は禁止
- 受け取り方法は、手渡しのみ
- 不妊手術(去勢・避妊)の実施
- 終生愛情と責任を持って育てること
- 誓約書に署名・捺印
- 譲渡に関わる費用については両者で確認と話し合いで決定
ペットショップ
譲渡の流れ
- ウェブサイト上で希望の猫が決まったら、フォームにて問い合わせ
- ショップより、電話で詳細の確認連絡
- ペットショップの規定に従い譲渡決定
猫カフェ
譲渡の流れ
- ウェブサイト上あるいは直接来店して希望の猫があれば、スタッフ、お店に連絡
- 面談、証明書類確認により譲渡決定
飼い主になるための条件
お店によって、条件、譲渡時の費用が異なります。
また、入店に年齢制限のあるお店がありますので、事前にご確認ください。
- 譲渡に際した年齢制限あり
- 完全室内飼いであること
- 飼育可能な住宅環境であること
- 定期検診や獣医療の必要性を理解し、医療を受けさせること
- 終生愛情と責任を持って飼育すること
- 家族全員の同意が得られていること
- 誓約書への記載
まとめ
どの機関・施設でも共通して、
飼い主となるための条件が厳しくすべてをクリアしていることが必須です。
一度は保健所に収容されるはずだった猫が、再び飼育放棄で戻ることに
なってしまうことを考えると、当然のことかもしれません。
里親して引き取りを希望したときに、 お金が一切かからないと思いがちですが、
完全に無料で譲渡される施設は少ないです。
費用については、譲渡するまでにかかった手術やワクチン等の医療費、
食事やトイレにかかった経費は応募者が負うべきものという考え方です。
そしてこの費用は、次に救う猫のために使われます。
条件の中で特記すべきは、年齢制限です。
特に小さい子供のいる家庭や、60歳以上の方が飼い主となる場合、
譲渡ができないケースがあります。
せっかく迎え入れたいという純粋な気持ちがあっても、
報われないのは辛いことです。
一匹でも多くの猫が幸せに暮らせるように、この条件に納得いただける家庭に
引き取ってもらえることを願います。
※上記の施設では、譲渡会等のイベント等を行っている場合があります。
各ウエブサイトを参照してください。
関連記事:【猫好きさん猫ほしいさん】『猫に好かれるための7つの習慣』
そして最後に。
いくら気持ちがあって、猫ちゃんを迎え入れたとしても
いつかは必ず、猫ちゃんとの別れが訪れます。
飼い主である以上は、愛する子が迷わずに虹の橋を渡れるように、毅然と行動しなくてはいけません。
そんなときどうしたらいいか?こちらで詳しく解説しています。
その他県、市の動物管理センター一覧
NPO法人、保護施設
| 千葉県柏市、岐阜市、名古屋市 | NPO法人犬と猫のためのライフボート |
| ふじみ野市 | NPO法人ペット里親会 |
| 笠間市川越市 | NPO法人いばらきの犬と猫 |
| 札幌市 | NPO法人猫と人を繋ぐツキネコ北海道 |
| 北海道夕張郡長沼町 | NPO法人HOKKAIDOしっぽの会 |
| 岐阜県大垣市 | NPO法人あすねこ |
| 岐阜県高山市 | NPO法人もふっこひだ |
| 愛媛県松山市 | NPO法人えひめイヌ・ネコの会 |
| さいたま市 | ティアハイムさいたま |
| 岡山市 | NPO法人 犬猫愛護会 わんぱーく |
| 愛知県みよし市 | NPO法人三好ネコの会 |
| 福島県いわき市 | NPO法人動物愛護団体LYSTA |
| 札幌市 | NPO法人Nyapan Cat Rescue |
| 東京都大田区 | NPO法人spa |
| 福井市 | NPO法人福井犬・猫を救う会 |
| 茨城県取手市 | NPO法人ポチたま会 |
| 山口県周南市 | NPO法人ケダマの会 |
| 長野県上田市 | NPO法人一匹でも犬・ねこを救う会 |
| 千葉県船橋市 | NPO法人猫の森 |
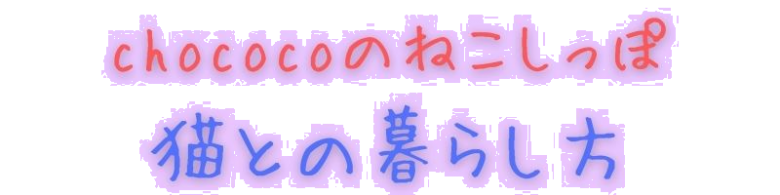




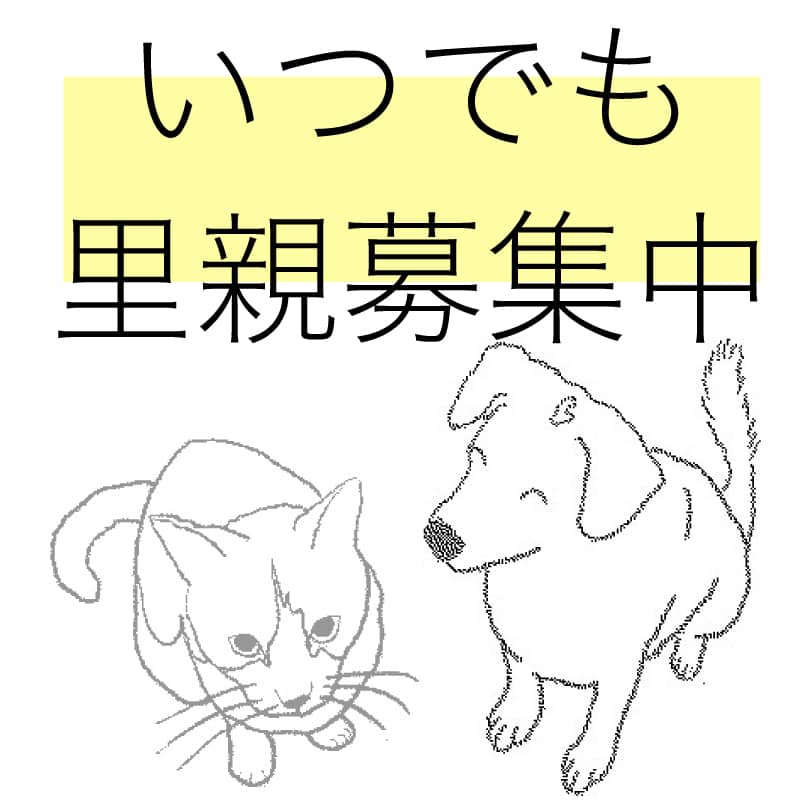







コメント