なんだかトイレが長い?
何度もトイレにいく。
トイレでニャアニャア鳴いてる・・・
それって、猫の尿路結石かも!?
猫によくみられる病気のひとつで、膀胱から尿道にかけての下部尿路で起こる病気を、下部尿路疾患(FLUTD)と呼び、その中でも特に発症することが多い、「尿路結石」は、膀胱でできた結石が原因で尿が出なくなったり、痛みが出ます。
結石ができた人は、わかると思いますが…、とっても痛い!
猫ちゃんも同じ痛みを味わうことになるんです(><)
そして、尿が排出できない状態が続くと、最悪は腎不全による尿毒症で死に至る場合も…
我が家のスコティッシュフォールド「ヨタロウ」がこの病気にかかったのは、生後6か月目のことでした。
なんとなく、トイレに行く回数が増えたなぁというのと、トイレに入るわりにはおしっこの塊がなかったり、塊が小さかったりして、様子がおかしいことはわかりました。
翌日、わずかなおしっこの塊に血尿がみられたので、すぐに病院へ連れていくと、「ストルバイト尿路結石症」と診断されました。
結論を先にいうと、尿路結石を治すには「療法食」によるpHコントロールです。
ここでは、「尿路結石」の原因、結石の見極め方、診断されてからの生活の仕方などについても解説します。
また他にも、猫ちゃんに水分補給させる方法や「療法食」について、詳しく解説します。
尿路疾患と診断されると、病院から療法食をとるように指導される場合が多いです。
尿路疾患について簡単にもっとわかりやすく知りたい方は↓参照ください。
参考記事:【かんたん解説】猫の尿路結石って何?
尿路結石の原因

結石が尿道内に詰まる原因は、以下のものが考えられます。
この中でも、「体質」と「たべもの」の影響を強く受け、それらによって尿pH(ペーハー)、つまりおしっこのpHが偏ることで結石ができるとされています。
※ストラバイトとも言いますが、当サイトでは「ストルバイト」に統一します。
・尿pHが酸性に傾いて、尿中のカルシウムが結晶化してできる「シュウ酸カルシウム」結石
アメリカの調査で猫の結石3940検体のうち、2018年においてはストルバイトが54.5%、シュウ酸カルシウムが37.7%の比率だったとされています。その他にもわずかな比率で尿酸やアパタイト、シリカといった種類の結石も存在します。
我が家の猫ヨタロウの結石は、尿pHがアルカリに傾いたことによる、「ストルバイト結石」でした。
参考:Companion Animal Practice(ロイヤルカナン上田)|シュウ酸カルシウム結石に対する食事管理、京都大学舟場・阿部|ネコの尿石症、Kopecny L, Palm CA, Segev G,Larsen JA, Westropp JL. Urolithiasis in cats: Evaluation of trends in urolith composition and risk factors (2005-2018)
尿路結石にかかりやすい猫は??
遺伝的要素として、罹りやすい猫種が研究によりわかっています。
一般的に尿路結石は、猫の種類、性別に関係なく発症の可能性があるといわれていましたが、2014年麻布大学附属病院での、尿路結石と診断された猫とその品種についての調査によると、雑種では罹患する数は少なく、純血種の中でヒマラヤン,アメリカンショートヘアー,そしてスコティッシュフォールドの順で罹患しやすいという調査結果が得られました。
また、年齢には関係なく、オスメスではオスの方の尿道が細く長いことから、結石がつまりやすいこともわかっています。
出典:麻布大学附属動物病院|麻布大学附属動物病院における猫の尿管結石の好発品種に関する検討
尿路結石の見極め
これまでの経験からおしっこやうんちを毎回確認することが大切だと思っています。
いつもとくらべて量や色に違いがないかの確認が、早期発見の鍵!
我が家でも血尿を見たときから、確認することを習慣付けています。
結石ができる兆候は、
・なんとなく落ち着かない、ソワソワする。
・おしっこのあと猫砂を確認すると、おしっこの量がほんの少し、あるいはまったくない。
・おしっこの跡が赤い(血尿)
・何度もトイレに行き、そのたびに痛そうにお尻を上げたり、鳴いたりする。
・お尻回りをなめることが多くなる。
血尿は白い猫砂だと分かりやすいのですが、我が家は当時、茶色のトイレに流せるタイプの砂でした。
それでも、よく見ると血尿らしいことはわかりました。
ソワソワして何度もトイレに行く、おしっこの量が少ないと感じた時はだ尿路疾患を疑った方がよいかもしれません。
また、結石ができる場所で痛みの有無があり、痛みのために「にゃあにゃあ」鳴くこともあります。
ヨタロウの場合も頻繁ではありませんでしたが、何度かトイレで鳴いているのを確認しています。
いずれにしても上のような兆候があれば、すぐ獣医師の診断を受けてください。
尿路結石かな?と思ったら
上での兆候が見られたら、躊躇せずにすぐ病院へ直行です。
病院で尿検査することになりますが、なかなかおしっこできないんですよね。
家でした、おしっこをスポイトなどで吸って、こぼれないように容器にいれるなどして持っていければベストです。できなければ、おしっこのついた猫砂の塊やシートを持っていくとよいかもしれません。
尿路結石と診断されたときの治療は、ストルバイト結石の場合は、おしっこのpHを整えてあげることで、おしっこの中で結石を溶かすことが期待できます。
ただし、ストルバイト結石が大きかったり、シュウ酸カルシウム結石は溶解が困難なため、症状に応じて手術が必要な場合があります。
各ミネラル成分やイオンバランスを特別に調整した下部尿路疾患用の「療法食」に切り替えることで、おしっこの状態を整えることがとても大切です。
定期的に尿検査をして症状が治まっているようなら、通常の食事に戻すことが可能なこともありますが、体質的に結石ができやすいような場合は、我が家のヨタロウのように療法食を続けなくてはいけないケースもあります。
ヨタロウの場合、療法食を1週間程度続けて尿量が元に戻ったことから、さらに1か月後、通常食に戻しました。
しかし、またすぐトイレの回数が増えた上に、尿量が減ってきたんです。
改めて病院で診察をうけると、再発傾向があって、療法食を続けるよう指導がありました。
それ以来十数年、ずーっと療法食を食べさせ続けて、その後の再発はありません。
ちなみに、療法食を続けるデメリットは、費用以外にはありません((>_<))
いずれにしても、一度結石と診断されて治療をされた猫ちゃんであれば、定期的に診断を受けることが大切です。
療法食はカロリーが高めのため太ってしまったり、猫ちゃんによっては食べ続けることのリスクも考えられます。
くれぐれも定期的な健康診断で、療法食を継続するのか、一般食に戻すかの指示を受けてください。
尿路結石の予防

尿路結石の予防は、とにかく結石を作らないことと、結石をためないことです。
そのための大きなポイントは、こまめな「水分補給」です。
水分をとることは、当然おしっこの量が増え、その際に結石の元になる結晶や細菌などを体外へ排出します。
ただ、水をよく飲ませることが望ましい一方で、なかなかそうもいきませんよね。
そこで、水分を補給するためには、ウェットフードの併用がおすすめです。
その際にも我が家では「療法食」のウェットフードを与えます。
そして普段、給水皿でなかなか水を飲んでくれない猫ちゃんには、常に水が循環して衛生的で、しかも「チョロチョロ」と水の音がする「自動給水器」に興味を示して、飲んでくれる子もいるようです。
試してみるのも良いかもしれませんね。
他にも、おしっこをためすぎないために、トイレしやすい環境も大切です。
常にきれいに。
トイレがきれいなのに、猫ちゃんがおしっこをしない場合、猫砂が気に入らなかったり、設置場所が落ち着かないといったケースも考えられます。
猫ちゃんが興味を示しそうな砂を試してみたり、ちょっと隠れられるような場所に移してみる、フルカバーのトイレに変えてみたりしてください。
猫の尿路疾患は、遺伝的な体質によるものも大きいようです。
今、症状がない場合でも、猫ちゃんの「親」に疾患があるような場合には、下部尿路疾患に配慮した総合食も発売されていますので、そちらの食事をメインにすることもよいかもしれません。
参考:マークモーリス研究所 徳本|猫における水分摂取の重要性
診断されてからの過ごし方~我が家の療法食
ヨタロウがトイレの中でモジモジしてた時は、ほんと、痛かったんだろうなぁ。。。と、こちらもおなかが、いや、胸が痛くなります。
それでも、今では看護師となった娘が子供の当時、ヨタロウの異変に気づいてくれたのが早くて、不幸中の幸いでした。
獣医師から、今後について指導されたのは、当面、療法食を与えること。
その際、紹介されたのは「ロイヤルカナン キャットフード pHコントロール2」でその名のとおり phをやや酸性に維持するための総合栄養食でした。
また、水分をこまめにとるために、水だけでなく「pHコントロール」のウェットタイプも与えてよいとも教えていただきました。
上でも紹介しましたが、1か月後に再発傾向があったため、以降十数年、ず~っと療法食生活です。
当時、ロイヤルカナンのphコントロールシリーズは、結石に対する効き方の違いで「phコントロール0,1,2」の3種類、そしてそれぞれにチキン、フィッシュの2種類のテイストでの展開がありましたが、最近、商品改良によりそれらを商品統一して、「ユリナリー S/O」という商品に切り替わりました。
現在は主治医の先生に相談し、ヨタロウの体重を考慮してその、カロリーオフタイプにしています。
我が家は、ヨタロウの他にアメショのショコラがいるのですが、多頭飼いの悩みである「盗み食い問題」があります(^^;
ショコラは尿路疾患の問題がないため、普通の食事を与えているのですが、ヨタロウがそれを盗み食いしてしまうことがあるんです。
主治医からは「ある程度」であれば問題ないだろうと………
とはいえ、ヨタロウが盗み食いしないように、食事の場所を変えています。
運よく?ちょっとぽっちゃりなヨタロウには登れない高さのテーブルがあって、ショコラはジャンプすれば登れるんです。
そこでショコラに食事してもらうことで、ヨタロウの盗み食いを防ぐことができました。
きっと、運動量の多い猫ちゃんだと厳しいですね。
まとめ
今回は尿路結石にかかりやすい猫種と原因、対策、予防について解説しました。
尿路結石にかかりやすい、ヒマラヤン,アメリカンショートヘアー,スコティッシュフォールドを飼っている家庭では、以下のおしっこの様子を、こまめにチェックするとよいです。
・トイレが長くないか?痛がって鳴いていないいないか?
・おしっこのあと、血が混じってないか?
・お尻回りをなめてないか?
このような兆候が少しでも見られたら、すぐに病院へ!!
今現在、疾患の診断がない猫ちゃんの防止対策には、こまめな水分補給の他、下部尿路疾患に配慮した総合食も売られていますのでお試しください。
かわいい猫ちゃんたちが長生きできるよう、日ごろからのチェックが大切です。
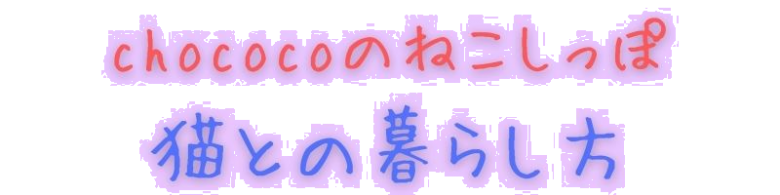
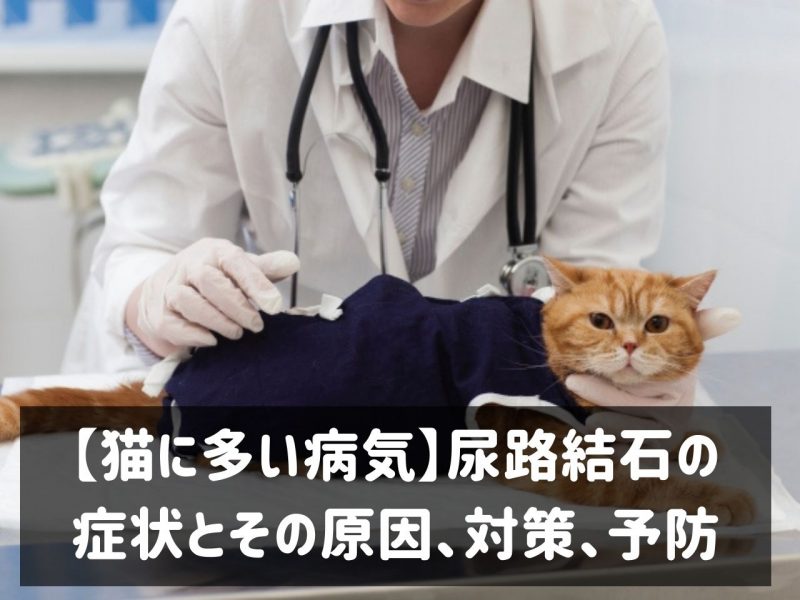


コメント