猫ちゃんの食事、健康なうちはそれほど気にしないのですが
ある時、猫ちゃんを抱っこしたときにふと、

なんだか体が大きくなってきたような・・・?
とか、

最近、やけに重くなったかな・・・
と感じるようになったり、
健康診断で獣医さんに

太りすぎです!
といわれて、その時初めて『食事のあげすぎ』に気付くんですが、それならまだいい方。
調子が悪そうにしている猫ちゃんを病院へ連れて行くと、
「糖尿病」や「心臓や呼吸器の疾患」をおこしていた!なんてこともありえます。
そして内臓の病気だけでなく、目で見てわかる病気にもなることも・・・
我が家のスコティッシュのヨタロウは太ったせいでこんなことになりました。
こちらの状況と結果は、最後の方でご紹介しますが、
ともかくそうなる前に、心がけるべきことや対策について、ヨタロウの復活までの様子を交えて解説します。
ぽっちゃり猫ちゃんがいる家庭のみなさん、ぜひご参考ください!
また、『猫ちゃんにとって安心・安全な食事とは何か?』について、↓こちらの記事で解説しています。ぜひご参考ください!
肥満にさせない食事の回数は何回がいい?
ちなみに、猫ちゃんに食事を1日何回与えてますか?
朝晩の2回でしょうか?
それとも朝昼晩の3回?
何回与えるべきか調べてみると、いろいろな意見が見られます。
・子猫なら4,5回、成猫で2,3回。
・成猫は2回がいいというところもあれば、いやいや複数回に分けた方がいいとか。
アンケートなどでも1日に2回という家庭が多く、おそらくそれが、核家族においての現実的な回数なのではないかと思います。
しかし、そもそも猫の祖先であるヤマネコは
高タンパク・低炭水化物の高水分(ウエット)の食物を1日に何回にも分けて摂取する動物である。
そして、人と同様に
猫も健康的に体重を維持するには、1日に少量の食事を頻繁に与えるべき。
引用:ILLINOIS univ.|Smaller meals more times per day may curb obesity in cats
以上の理由から、獣医さんやフードメーカーでは、以下を推奨しています。
とは言っても、日中不在にしているなど、なかなかその通りにするのは難しいですよね。
上のイリノイ大学のSwanson氏も、「実際の生活では、特に複数のペットがいる家庭では、それほど簡単ではない。」と言っています。
我が家は家族の休みがバラバラのため、日中いるときに3回与えていますが、
どうしても誰もいないときは2回になってしまうこともあるんです。
日によって回数が違ってしまうのは、仕方ないよな~と😣
でも、一人暮らしで1日1食しか与えられないとなると、さすがにそれは問題かも!?
普段、仕事や学校で決まった時間に与えられない方には、ぜひ自動給餌器をおすすめします。
こちら↓で自動給餌器を詳しく解説しています。
食事の量は?種類は?
猫の祖先、リビアヤマネコは、厳しい環境の砂漠にいて、カロリー消費が少ない体であるために、「ねこは痩せにくい」というのは有名な話です。
なので、いったん太ってしまうと、体重を戻すのが難しい・・・
では食事の量はどれくらいが肥満対策として理想なのでしょうか?
環境省では動物愛護管理法ペットフードのガイドラインの中で、痩せすぎや太りすぎにならない、食事量の算出方法を次のように定めています。
①安静にしているときに必要なエネルギー量
安静時のエネルギー要求量 【RER】(キロカロリー)= 体重(kg)×30+70
②日々の生活に必要なエネルギー量
1日あたりのエネルギー要求量【DER】(kcal)= 【RER】×係数(※)
※係数とは、猫のライフステージによって決められた「活動係数」
| ライフステージ | 係数 |
| 避妊・去勢していない成猫 | 1.4 |
| 避妊・去勢済みの成猫 | 1.2 |
| 肥満傾向 | 1.0 |
| 高齢猫 | 1.1 |
| 妊娠中 | 2.0 |
| 授乳中(自由採食) | 2.0~6.0 |
| 成長期 4か月未満 | 3.0 |
| 成長期 4~6か月 | 2.5 |
| 成長期 7~12か月 | 2.5 |
③1日当たりの食事量
1日あたりの食事量 = A ÷ B × 100
A:1日あたりのエネルギー要求量【DER】(kcal)
B:キャットフードに表示された代謝エネルギー【ME】(kcal/100g)
計算例 体重5kgの猫(避妊去勢済)
※体重が2~45kgの場合のみ計算可能
②1日あたりのエネルギー要求量【DER】= 220 × 1.2(係数)= 264 (kcal)
※係数は「避妊去勢済み成猫の場合」:1.2
成長段階や活動量によって変わります。詳しくは獣医師に相談しましょう。
③1日あたりの食事量 = A【DER】 ÷ B【ME】(kcal/100g) × 100
= 264 ÷ 400 × 100 = 66 (g)
※例として代謝エネルギーが400kcl/100gのフードを与えたとき
でも実際にフードに記載されている食事量(給与量)を見ると、体重4kgで59gなので、計算式の値より少なめになっているのです・・・?!
フードメーカーは、給与量を少し多めに記載しているのでは?と疑っていたのですが(^^;
失礼しました。
そんなことはなくて、安心しました。
計算式はあくまでも、痩せすぎ太りすぎにならない目安であって、例えば食事の回数によってカロリー消費が異なることや、猫の種別によっても必要カロリーが異なる、などフードメーカーによっても、考え方に違いがあるようです。
もちろん、猫ちゃんの体質など成長段階や活動量によりますので、環境省でも「詳細は獣医師に相談」としています。
なので、念のためこのガイドの計算式は目安ということで、基本はフードの給与量通りに与えてみて、猫ちゃんの体重の増減に合わせて、給与量を変えていくのがよさそうです。
参考・出典:環境省|飼い主のためのペットフード ・ ガイドライン~犬・猫の健康を守るために~


どれくらいから肥満なの?
猫の肥満度合いは、猫の種類によって大きさが違うので、体重だけで太っているかどうかは、わかりません。
そこで、下図の「ディコンディションスコア(BCS)」を参考に判定します。
見た目と触った状態で5段階に分類され、猫を上から見たときに、腰に適度なくびれがあり脂肪分がわずかであることです。
4番以降から肥満と判断します。
一見理想的なBCS3であっても、おなかから脂肪の塊が垂れている猫ちゃんは、BCS4に分類されます。
うちの子がそうでしたwww
多頭飼いでの食事について
多頭飼いのお宅ではあるあるかもしれませんが、残ってる食事をいつの間にか盗み食いする食いしん坊がいるんですw
うちの場合、ショコラがちょいちょい残して、後からまた食べたいというタイプです。
すると食いしん坊のヨタロウが、ショコラのを盗み食い、というか堂々と食べ始めますww
見張っていたはずが、うっかり見逃していて、ヨタロウが舌をペロリとしながら、ショコラの食器から離れる姿を目にすることも度々でした。
肥満による弊害
肥満による弊害は人間と同様、糖尿病や心臓・呼吸器の疾患、そして肝機能障害のリスクが大きくなります。
肝機能障害では、猫特有の脂肪肝(肝リピドーシス)という、最悪は命に係わる重大な病気になる可能性があります。
そのほかにも、体重が増えて手足や胴の関節に負担がかかることで、発症する病気もあるんです。
そういう点では、人間も一緒ですね。
スコティッシュフォールドの病気
我が家の黄色い方、ヨタロウ(♂)は、外見からわかる通り、折れ耳のスコティッシュフォールドです。
スコティッシュフォールドは、ご存じの方も多いと思いますが、耳の軟骨の異常を引き起こす遺伝的な欠陥があります。
そのため、「骨軟骨異形成症」という、関節が変形して固く腫れたりすることで痛みが出る病気を発症する可能性が高いのです。
もちろん、必ずかかるわけではなく、またかかっても痛みの度合いも猫ちゃんによるのですが、一度かかってしまうと、今のところ直す方法がありません。
そのため、少しでも病気のリスクを軽減するために、しっかりと体調管理をしなくてはいけないのです。
参考:international cat care|スコティッシュフォールドの病気-骨軟骨異形成症
ヨタロウの肥満と診断結果
ここで、再びわが家のヨタロウが、足を引きずるようになった出来事についてのお話しです。
ヨタロウとショコラには、カリカリとウエットの組み合わせで与えています。
フードに記載されている「ドライ製品とウエット製品を混ぜて給与する場合」の給与表に従って、1日分の量を2~3回に分けて与えていますが、うちの猫たち、「標準の量では足りない!」と言って、食べ終わった後にもすり寄ってくるんです。
そのため、以前は「じゃぁ、ちょっとだけね。」といって、ついつい標準以上の量を与えてしまうこともありました。
以前からショコラよりも運動量が圧倒的に少なく、盗み食いまでしてしまうヨタロウは、コンスタントに体重を伸ばし続け、6年前の健康診断でついに体重が5kg近くにもなって、肥満と診断されました。
主治医からは、ヨタロウを太らせてはいけないと再三注意を受けていましたが、この時は垂れ下がったおなかにある、白い脂肪のレントゲン写真を診せられ、
「このままじゃ、大変な病気になるよ!」
とかなり強めに、痩せるよう指導が入りました。
食事量を減らし、盗み食いしないよう監視してなんとか4.5kgまでは落ちたのですが、そこか先は一進一退のまま、ついに一昨年、ヨタロウに異変が・・・
ぴょこぴょこと足を引きずって歩くようになったんです。
常にではないのですが、どうやら左前足の関節が痛いらしく、引きずってしまうんです。
レントゲンでは、足の関節に変形の兆候がみられ、どうやら「骨軟骨異形成症」になり始めているとのことでした。
ただし、体重を軽くすることで関節への負担が減り、痛みを和らげて普通に生活できるようになるとの励ましもいただき、そこから気持ちを入れ替えてしっかりと体重管理を徹底しました。
医者の指示でフードをライト系に変え、盗み食いの監視を強化しました。
そのうち、ヨタロウがあまりジャンプが得意ではないところを利用して、ショコラに高いところで食事してもらうなどして、盗み食いされることはほぼなくなりました。
あとは、追加のご飯をねだる甘えた声に耳を塞ぐことができるか?
肥満対策の食事
今回の対策では、量の制限だけでなく、カリカリを同じシリーズのカロリーオフタイプの「ライト」に切り替えました。
その上で与える量を「標準」用ではなく、「太り気味」用のより少な目に。
たとえ、すりすり甘えてきても、グッとこらえて我慢がまん・・・
その甲斐あって、一時は3.9kg、夢の3kg台までダイエットできました。
実はヨタロウ、2021年2月に胃腸炎にかかって3kg近くまで痩せてしまったんです。
そこから元気になって、現在3.5kg!!
ようやく理想の体に戻ることができました!!
まったく今では足を引きずることがなくなり、自分からキャットウォークを歩いたり、以前のお気に入りだったハンモックにも登るようにもなりました。

まとめ
あらためて、食事を複数回に分ける理由をまとめると、
・猫が自由に食事を与えられると肥満になりやすい
・食事間隔を短くすることで空腹感が減り、食事総量が増えない
・水分量の多い食事(ウェットフード)が満足感を与える
肥満にならないように食事を管理することは、本当に大変なことだと思います。
なんせ可愛いあまり、ついつい甘やかしてしまいます。
でも、病気になってしまっては元も子もありません。
飼い主の責任として、時には心を鬼にして!w
我が家では、現在は私が在宅の仕事ということもあり、1日3回、あるいは昼食と夕食はそれぞれ2回ずつに分けて・・・つまり1日5回にして与えています。
確かに、以前に比べてそれほど「ごはん、ちょーだい!!」がなくなってきました。
猫ちゃんの健康全般の管理で一番大事なのは、こまめな体重測定です。
猫ちゃんを抱っこして測定すれば、自分の体重管理もできて、一石二鳥!!www
当たり前ですが、食事量は給与表に従い、きっちりスケールで計量して与える。
太り気味の兆候がでてきたら、すぐ主治医に相談すべきです。
どうしても、口が寂しい猫ちゃんには、カロリーオフのライトフードはおすすめです。
また、カリカリだけよりも、カロリーの少ないウェットフードを併用すると、お腹が満足するだけでなく、尿路疾患対策の水分補給にもなります。
上で紹介した通り、太らせないために、食事回数を増やすのが望ましいのですが、どうしても各家庭の生活ペースによりますね。
普段、仕事や学校で決まった時間に与えられない方には、自動給餌器がおすすめです!
2022年の3月には13歳になる、ヨタロウとショコラ。
これからもますます元気でいられるように、健康管理をしっかりしていきます。

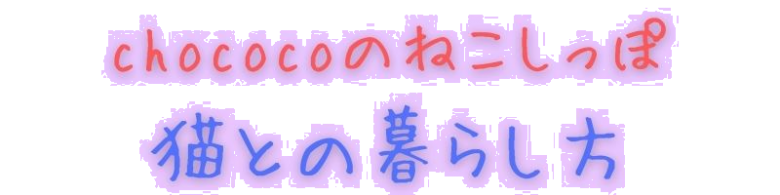





コメント